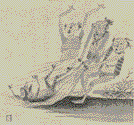
今から約100年くらい昔のことです。上小船津浜という村に、上新保という「あみもと」の家がありました。
上新保さんと近所の人たちは、毎日のように漁に出掛け、網に引っかかってくる魚を見ては喜んでいました。そして、とれた魚の半分は上新保さんに、残りの半分は手伝いの近所の人たちに分けてやり、生活を成り立たせていました。
ある日のことです。いつものように上新保さんたちは、漁に出掛けていきました。そして、
「今日も、いわしがいっぱいとれるといいなあ。」
「おれ昨日、くじらをつかまえた夢を見たでね。この舟の倍もでっかいやつでね。」
と、まじめな顔で話し合っていました。ところがやがて不思議なことが起こったのでした。
「せぇのぉ ヨイショ せぇのぉ ヨイショ」
と、力を合わせて網を引きますが、いつもと違って大変重いのです。やっとの思いで網を引き上げてみますと、その中に1匹の「すじんこ」(別名カッパ)が引っかかっていました。
気味の悪い「すじんこ」を見て、人々は「殺すか」「いじめるか」などと言っていましたが、さすがは、あみもとさんです。すじんこを網からといて、海へ放してやりました。
そして、その不思議な出来事から時間がたち、夜になりました。仕事を終え、疲れきった体を布団にあずけ、あみもとさんはいつの間にか眠りに入りました。すると、夢の中に昼間のすじんこが姿を現しました。どうやら夢知らせのようです。
さっきはどうもありがとうございました。そのお礼に、のどけの薬(今の口内炎やのどの薬)の作り方を教えましょう。お役に立てればと思います。まず、これとこれを混ぜて、ああやって、こうやって、これでできあがります。この薬で皆さんの、のどを治してやってください。」
と言って、夢の中から立ち去りました。
あみもとさんは、半信半疑で、その薬を作ってみました。出来上がった薬は、黄色みがかっただいだい色で、ややすっかい粉の薬となりました。そこで早速つけてみることにしました。
薬はのどの奥につけないと効果がありません。そこであみもとさんはいろいろと工夫した末、細い竹の先を平らに切り、その先にのどけの薬を載せ、ふっと吹くと、見事にのどの奥までいくことが分かりました。
早速ためしにつけてみると、涙がでるほどしみて、よだれがだらだら出てきてしまうのです。「出てくるな」といっても出てくるのでした。
しかし、その効果といったらすごいものでした。魔法にかかったように、みるみるうちに治ってしまうのです。
それからというものは、この「のどけの薬」は大変な評判になり、近隣ばかりでなく、遠く県外からも買い求めにやってきました。こうなると「のどけの薬」もだんだんと、大量に作らなければならなくなり、とうとう元になる薬がなくなってしまいました。
そこで、直江津の金谷薬屋へ行って6、7種類の元になる薬を買って来て、これを調合しました。作り方は、「やげん」を用いて、これをすりつぶして粉にし、これを「ちぎ(はかり)」にかけて計り、1服ずつ盛りつけ、更にこれを大きな薬にまとめて売るようにしました。
戦争中の昭和17年ごろ、元になる薬が手に入らなくなり、とうとうこの「のどけの薬」を作ることをやめてしまいました。
(語り手 土底浜 柳沢美都世 昭和56年 70歳、上越市 富永 浩 昭和56年 62歳)
(出典:昭和63年5月30日発行 大潟町史)