毎年3月から4月は人や物の移動が活発になることから、新型コロナウイルス感染症への感染リスクが高まることが心配されます。
新潟県では、昨年12月17日から新型コロナウイルス感染症の警報を発令しています。首都圏や関西の大都市でも、緊急事態宣言が発令され、外出自粛などが行われています。
新しい生活様式に慣れてきたかと思いますが、引き続き手洗いやマスクなど、感染予防に努めましょう。
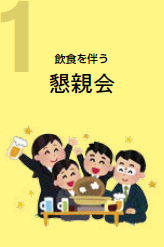

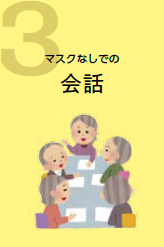
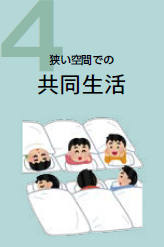
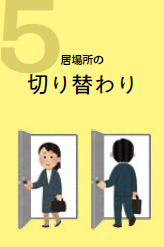
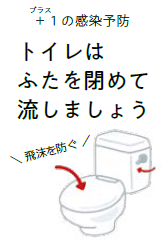
新型コロナウイルスの感染経路として、飛沫感染のほか、接触感染に注意が必要です。花粉の時季は特に目が痒くなったり、鼻水がでたり顔に触る回数が増えますが、意識してなるべく触らないようにしましょう。
市では、ワクチンを早くに接種することができるように、準備を進めています。
原則として住民票所在地の市町村で接種します。ワクチン接種開始の時期が決まり次第、接種券の送付を行います。
3月中旬から高齢者を対象とした接種券や案内チラシを発送する予定です。
問合せ:新型コロナウイルスワクチン接種事務室(電話:025–526–5111、内線1805)
問合せ:市民課(電話:025–526–5111、内線1744、1130)
ガス水道に関すること:ガス水道局料金センター(電話:025–522–7030)
3月から4月は、引っ越しなどの手続きで窓口が大変混み合います。手続きは、待ち時間を除き平均30分程度かかりますので、余裕をもってお越しください。
(注)住所の異動のある人は、住民基本台帳法に基づき、転出・転入の手続きが必要です。進学や就職などで引っ越しをされる人は、忘れずに住所の届け出をしてください。
月曜日~金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分。ただし、3月28日(日曜日)と4月4日(日曜日)は、市役所木田庁舎、各総合事務所などの窓口を開設します(詳しくは「年度末・年度始めの日曜日に窓口を開きます」をご覧ください)。
市民課、各総合事務所、南・北出張所
転出時は、住民異動届が必要です。届け出により転出証明書を発行しますので、転出先の市区町村へ提出し、転入手続きをしてください。
転出の場合は、異動予定日のおおむね2週間前から異動予定日までに手続きをしてください。転入・転居の場合は、新しい住所地に住んでから2週間以内に手続きをしてください(新しい住所地に住む前の手続きはできません)。
マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど本人確認ができるものが必要です。マイナンバーカード、住民基本台帳カードを所持している人は必ず持参してください。
転入・転出などの他に手続きが必要な場合があります。該当する制度やサービスなどを利用している人は手続きをしてください(詳しくは5ページ)。
引っ越しの日が決まり次第、早めに申し込んでください。事前申込した場合は、日曜日や祝日も作業を行います。ガス水道局料金センターに問い合わせるか、ガス水道局ホームページの「お申し込みフォーム(外部リンク)<外部リンク>」から申し込んでください。
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、窓口に行かずにできる手続きなどを活用ください
戸籍の謄本・抄本、住民票の写しなどの証明書は郵送請求ができます。
マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアで各種証明書を取得できます。
マイナンバーカードを取得していない人を対象に、地方公共団体情報システム機構から、令和3年1月から3月にかけて順次、カードの申請に必要なQRコード付き交付申請書が送付されます。
交付申請書を使い、郵送やスマートフォンなどにより、ご自宅から申請することができます。
市民課と各総合事務所では、マイナンバーカードの申請手続きや受け取りの窓口を土曜日・日曜日にも開設しています(各総合事務所は事前予約が必要です)。
3月と4月の開設日時:3月13日(土曜日)、28日(日曜日)、4月4日(日曜日)、24日(土曜日)の午前9時~午後5時
(注)土日窓口は、通常は毎月第2土曜日と第4日曜日の開設ですが、今回は変更となります。
問合せ:市民課(電話:025-526-5111、内線1122、1745)
開設日時:3月28日(日曜日)、4月4日(日曜日)午前8時30分~午後5時15分
下記の窓口で、各種届け出などの手続きができます。
詳しくは、市役所(電話:025-526-5111)の各担当課または記載の電話番号へ問い合わせてください。
| 場所 | 開設窓口 | 手続きができる届け出など | 問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|
| 市役所木田庁舎 | 1階 | 市民課 | ・住民異動届(転出、転入、転居など) (注)他市町村へ照会が必要な場合や、転出証明書を持参しない特例転入は手続きができない場合があります。 |
内線1130、1122 |
| ・ 戸籍届(出生、死亡、婚姻など) | 内線1309 | |||
| 戸籍謄抄本(除籍、原戸籍を含む)、住民票の写し(広域交付を除く)、印鑑登録証明書などの交付、印鑑登録 | 内線1123、1744 | |||
| ・マイナンバーカードに関すること ・電子証明書に関すること |
内線1122、1745 | |||
| パスポートセンター (市民課前) |
・一般旅券(パスポート)の交付(受け取り) (注)申請はできません。交付の際は、事前に収入印紙と新潟県収入証紙を購入してお越しください。 |
内線1746 | ||
| 生活環境課 | ・ごみの分別方法や収集日程の情報提供および啓発業務 ・し尿くみ取りに関する相談、届け出(新規、廃止) |
内線1020-1633、1020-1367 | ||
| 危機管理課 | ・防災ラジオの配布(一部区域を除く合併前上越市の区域への転入者)と回収(転出者) ・防災ガイドブック・避難所マップ、津波・洪水ハザードマップの配布 |
内線1525、1734 (注)問合せは平日のみ |
||
| 国保年金課 | 国民健康保険の各種申請、相談 | 内線 1139、1661 | ||
| 国民年金の加入届、免除申請、学生納付特例申請 | 内線1144 | |||
| 後期高齢者医療制度、老人医療費助成制度の各種申請、相談 | 内線1137 | |||
| 福祉課 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、重度心身障害者医療費助成(県障)、自立支援医療(更生、育成、精神通院)の各種申請、交付、相談 | 内線1506、1118 | ||
| 特別障害者手当などの各種手当、障害福祉サービスの各種申請、相談 | 内線1651、1507 | |||
| 高齢者支援課 | 介護保険の各種申請 | 内線1158、1193 | ||
| 高齢者福祉サービスの相談 | 内線1153 | |||
| こども課 | 児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成、子ども医療費助成、妊産婦医療費助成の各種申請、相談 | 内線1711、1162 | ||
| (健康づくり推進課) | 乳幼児健診、児童に係る予防接種の相談、母子健康手帳の交付 (注)窓口はこども課です |
内線1161 | ||
| 2階 | 税務課 | 所得、資産、納税証明書の発行 | 内線1241 | |
| 収納課 | 市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、市営・県営住宅(駐車場)使用料の納付受付 | 内線1230、1232 | ||
| 保育課 | 保育園、認定こども園の入園相談 | 内線1848 | ||
| 教育プラザ | 学校教育課 | 放課後児童クラブ利用申請、相談 転入学の案内、相談 (注)3月28日(日曜日)のみ開設します。 |
電話:025-545-9244 | |
| ガス水道局 | 料金センター | 転居などに伴うガス、水道の開閉栓、料金の納付受付 | 電話:025-522-7030 | |
(注)各総合事務所、南出張所(電話:025-525-4151)、北出張所(電話:025-544-2111)でも市役所木田庁舎と同様の業務(パスポートの交付を除く)を行います。また、合併前上越市に住む人で、南・北出張所においてマイナンバーカードの交付を希望する場合は、3日前までに市民課(内線1103)へ予約してください。
市大雪災害対策本部と排雪5事業者との間に立ち、調整役を担っていただいた株式会社上越商会の 沢一弘さんに、今回の除排雪対応の舞台裏についてお話を聞きました。
沢一弘さんに、今回の除排雪対応の舞台裏についてお話を聞きました。
 沢一弘さん(写真右)と、今回初めて一斉排雪を経験した若きオペレーター・佐藤寛歩(ひろと) さん(写真左)。
沢一弘さん(写真右)と、今回初めて一斉排雪を経験した若きオペレーター・佐藤寛歩(ひろと) さん(写真左)。
昨冬の小雪から一転、1月7日から11日にかけての記録的な降雪により、道路除雪に加えての一斉屋根雪下ろし・排雪となりました。今回の大雪をどのように振り返りますか。
( 沢さん)降雪のピーク時には道路除雪が追いつかず、朝出ても昼も夜も出なければいけないような状況で、従業員は家に帰らずに会社に泊まり込みで作業を続けていました。家に帰れた人も、今度は出勤できなくなってしまい、会社で迎えに行くなどしてできる限り人員を確保しましたが、それでも足りないところは同じ人が2日、3日と連続して出動していました。
沢さん)降雪のピーク時には道路除雪が追いつかず、朝出ても昼も夜も出なければいけないような状況で、従業員は家に帰らずに会社に泊まり込みで作業を続けていました。家に帰れた人も、今度は出勤できなくなってしまい、会社で迎えに行くなどしてできる限り人員を確保しましたが、それでも足りないところは同じ人が2日、3日と連続して出動していました。
仮眠なども取られていたんでしょうが、体力的にも相当厳しかったことと思います。
( 沢さん)余剰人員が大勢いて、何班でもローテーションを組んで回せればいいんですが。除雪路線が多く、ローテーションが組めないため、そこで使う機械はその人専用になってしまうのが実際のところです。また、雪は最後に雪捨て場へ持っていきますが、ピーク時には24時間で1メートルも積もるような状況でしたから、雪捨て場までの道付けや、そこに至る幹線道路の除雪も進みませんでしたので、本当に困りました。
沢さん)余剰人員が大勢いて、何班でもローテーションを組んで回せればいいんですが。除雪路線が多く、ローテーションが組めないため、そこで使う機械はその人専用になってしまうのが実際のところです。また、雪は最後に雪捨て場へ持っていきますが、ピーク時には24時間で1メートルも積もるような状況でしたから、雪捨て場までの道付けや、そこに至る幹線道路の除雪も進みませんでしたので、本当に困りました。
そうした中、13日には一斉屋根雪下ろし・排雪の実施が決まりました。
( 沢さん)すでに道路除雪がひっ迫していましたので、屋根雪の状況を見ながら、「いつ声が掛かるか」と心配していました。いよいよ話が立ち上がったときには、やらなくてはいけないな、という思いでした。その時点では屋根雪が相当の量でしたので、排雪にどれくらいの日数が掛かるか、見当がつきませんでした。かき分けていくだけの道路除雪と違って、狭い町なかでの排雪は誰にでもできる作業ではありません。何せ9年振りでしたので、経験者の多くはすでに退職していますし、若い従業員は経験がないので分かりません。ですので、準備段階では作業の中心となる、排雪の経験のあるオペレーターの人選や機械の配置など、十分な打ち合わせを行いました。
沢さん)すでに道路除雪がひっ迫していましたので、屋根雪の状況を見ながら、「いつ声が掛かるか」と心配していました。いよいよ話が立ち上がったときには、やらなくてはいけないな、という思いでした。その時点では屋根雪が相当の量でしたので、排雪にどれくらいの日数が掛かるか、見当がつきませんでした。かき分けていくだけの道路除雪と違って、狭い町なかでの排雪は誰にでもできる作業ではありません。何せ9年振りでしたので、経験者の多くはすでに退職していますし、若い従業員は経験がないので分かりません。ですので、準備段階では作業の中心となる、排雪の経験のあるオペレーターの人選や機械の配置など、十分な打ち合わせを行いました。
排雪作業を拝見しましたが、狭い道路でロータリー除雪車の横や後ろにぴったりとダンプを付けて次々に雪を積んでいく様子を見て、技術の高さと段取りの良さに感心しました。
( 沢さん)今回の排雪は、9年前の排雪の経験がある5社で行いました。そうしたノウハウは各社持っていますし、どんな機械が会社にあって、それをどう組み合わせて作業を行うか、ということがポイントでした。ロータリーを使えば作業は早いですが、それに加えて、オペレーターとダンプの運転手が息を合わせて作業をするということが重要です。
沢さん)今回の排雪は、9年前の排雪の経験がある5社で行いました。そうしたノウハウは各社持っていますし、どんな機械が会社にあって、それをどう組み合わせて作業を行うか、ということがポイントでした。ロータリーを使えば作業は早いですが、それに加えて、オペレーターとダンプの運転手が息を合わせて作業をするということが重要です。
町なかでの排雪の技術は、どのように習熟されるのですか。
( 沢さん)通常の道路除雪は毎日出ますから慣れてきますし、幅員の広い道路の排雪であればさほど問題はないんですが、一斉排雪のような狭い道路での排雪は練習もできません。実地での経験が何よりも大切です。
沢さん)通常の道路除雪は毎日出ますから慣れてきますし、幅員の広い道路の排雪であればさほど問題はないんですが、一斉排雪のような狭い道路での排雪は練習もできません。実地での経験が何よりも大切です。
今回も、ベテランのオペレーターが「そうじゃなくて、こうやった方がきれいになるし早いぞ」と現地で若い従業員に教えていましたが、そうやって指導してもらわないと、技術は伝えていくことができません。この町に住んでいれば、今後も一斉屋根雪下ろしは避けては通れませんので、次の排雪に備えてオペレーターの若返りを図って、技術も高めていく、そこが一番の課題ですね。
そうした課題もある中、今回の排雪は、実質25日から27日までのわずか3日間で完了しました。
( 沢さん)一斉屋根雪下ろし当日までに降雪が落ち着いて、屋根雪の嵩(かさ)が減ったということもありますが、少しでも早く道路を開けようと、担当する路線が早く終わった業者からは、まだ終わっていない路線にヘルプに入ってもらうなど、5社の間でうまく連携が取れたと思います。何よりも、今回の排雪では事故が無くて本当に良かったです。私はそれを誇りに思いますし、排雪にあたった皆さんからも同じように思ってもらいたいです。みんな超一流です。
沢さん)一斉屋根雪下ろし当日までに降雪が落ち着いて、屋根雪の嵩(かさ)が減ったということもありますが、少しでも早く道路を開けようと、担当する路線が早く終わった業者からは、まだ終わっていない路線にヘルプに入ってもらうなど、5社の間でうまく連携が取れたと思います。何よりも、今回の排雪では事故が無くて本当に良かったです。私はそれを誇りに思いますし、排雪にあたった皆さんからも同じように思ってもらいたいです。みんな超一流です。